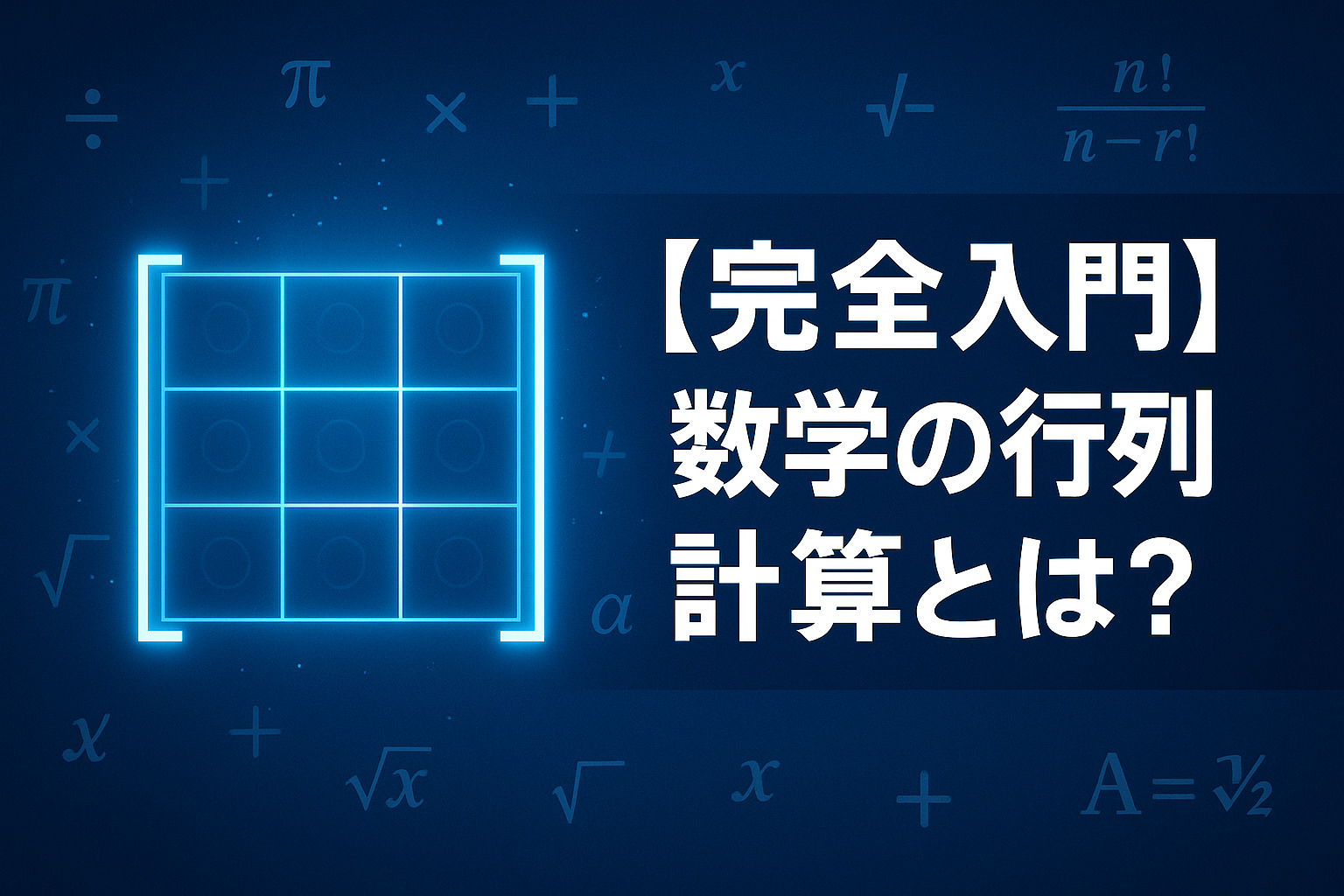「行列(ぎょうれつ)」と聞くと、「数学の難しい分野」というイメージを持つ方も多いでしょう。
でも実は、行列は私たちの身の回りでたくさん使われている、とても便利な道具なんです。
スマートフォンの画面回転、ゲームの3Dグラフィックス、GoogleやYouTubeのおすすめ機能、さらには天気予報まで——これらすべてに行列の計算が使われています。
この記事では、行列の基本から計算方法、実際の応用例まで丁寧に解説します。
行列とは?|数を整理整頓する便利な道具
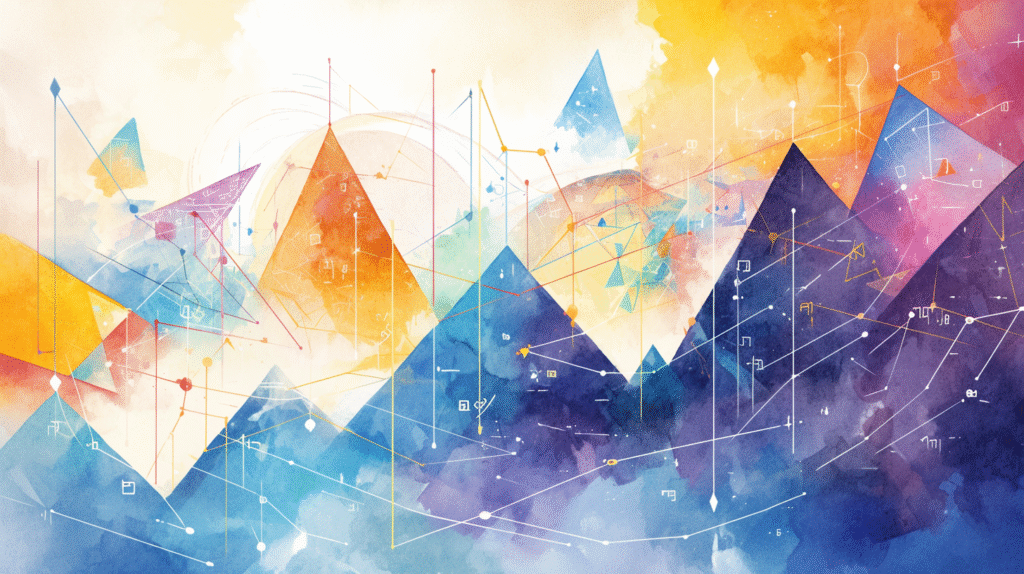
行列の基本的な考え方
行列とは、数や式を「行(横の並び)」と「列(縦の並び)」できれいに並べたもののことです。
まるで表やマス目のように、規則正しく数を配置します。
身近な例で考えてみましょう
クラスのテストの点数を整理する場合:
数学 英語 理科
田中 80 70 90
佐藤 75 85 80
これを行列で表すと:
[ 80 70 90 ]
[ 75 85 80 ]
となります。これが2行3列の行列です。
行列の表記方法
基本的な2×2行列の例
A = [ 1 2 ]
[ 3 4 ]
読み方と名前
- これは「2行2列の行列」または「2×2行列(にかけるに)」
- 左上から「1行1列目の要素は1」「1行2列目の要素は2」
- 下段は「2行1列目の要素は3」「2行2列目の要素は4」
いろいろなサイズの行列
1×3行列(ベクトル)
[ 5 10 15 ]
3×1行列(縦ベクトル)
[ 2 ]
[ 4 ]
[ 6 ]
3×3行列
[ 1 2 3 ]
[ 4 5 6 ]
[ 7 8 9 ]
行列が便利な理由
大量のデータを整理整頓
- たくさんの数値を見やすく整理
- 規則的な計算が簡単にできる
- コンピューターで処理しやすい
行列は単なる数字の並びではなく、規則に基づいて操作できる便利な構造です。
次に、行列同士でどんな計算ができるのかを見ていきましょう。
行列の基本計算|足し算・引き算・掛け算
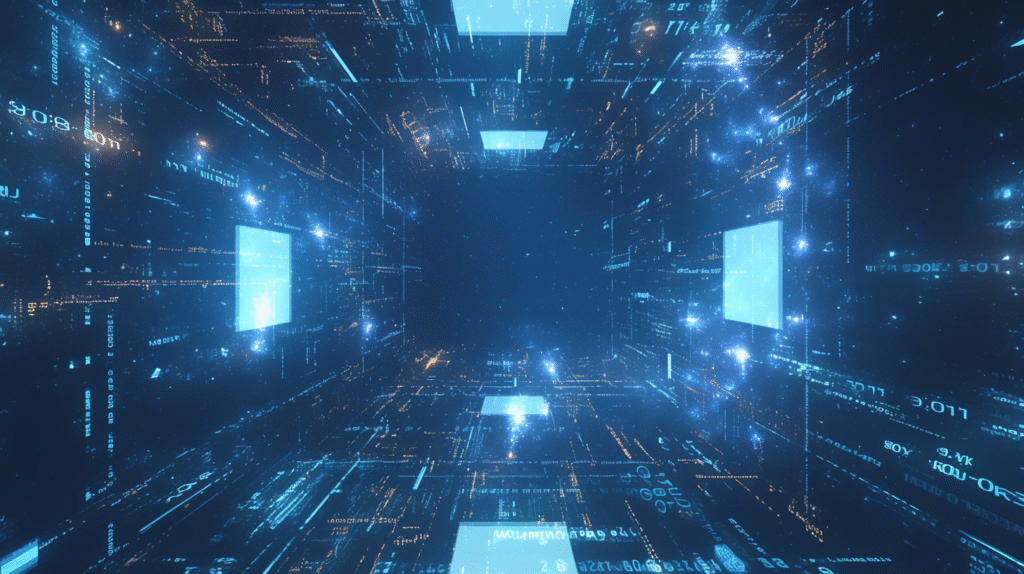
行列の足し算・引き算
行列の足し算と引き算は、とても直感的でわかりやすい計算です。
ルール:同じ位置にある数同士を計算する
足し算の例
[ 1 2 ] + [ 5 6 ] = [ 1+5 2+6 ] = [ 6 8 ]
[ 3 4 ] [ 7 8 ] [ 3+7 4+8 ] [ 10 12]
引き算の例
[ 8 10 ] - [ 2 3 ] = [ 8-2 10-3 ] = [ 6 7 ]
[ 12 15 ] [ 4 5 ] [12-4 15-5 ] [ 8 10]
重要な条件
- 足し算・引き算ができるのは「同じサイズの行列同士」だけ
- 2×2と3×3の行列は計算できません
具体的な応用例
テストの点数を例にしてみましょう:
1学期の点数: 2学期の点数: 合計:
[ 80 70 ] + [ 85 75 ] = [ 165 145 ]
[ 90 60 ] [ 80 90 ] [ 170 150 ]
スカラー倍(数をかける)
行列全体に同じ数をかけることを「スカラー倍」と言います。
計算方法 行列のすべての要素に同じ数をかけるだけです。
例:2倍にする
2 × [ 1 2 ] = [ 2×1 2×2 ] = [ 2 4 ]
[ 3 4 ] [ 2×3 2×4 ] [ 6 8 ]
例:半分にする
0.5 × [ 10 20 ] = [ 5 10 ]
[ 30 40 ] [ 15 20 ]
実用例
- 消費税を計算:値段の行列 × 1.1
- 割引を計算:値段の行列 × 0.8
- 単位換算:キロメートルの行列 × 1000 = メートル
行列の掛け算(積)
行列の掛け算は少し複雑ですが、ルールを覚えれば誰でも計算できます。
基本ルール
左の行列の「行」と右の行列の「列」を使って計算します。
2×2行列同士の掛け算
[ 1 2 ] × [ 7 8 ] = [ ? ? ]
[ 3 4 ] [ 9 10] [ ? ? ]
計算手順
左上の要素を計算 1行目 [1, 2] と 1列目 [7, 9] を使用
1×7 + 2×9 = 7 + 18 = 25
右上の要素を計算 1行目 [1, 2] と 2列目 [8, 10] を使用
1×8 + 2×10 = 8 + 20 = 28
左下の要素を計算 2行目 [3, 4] と 1列目 [7, 9] を使用
3×7 + 4×9 = 21 + 36 = 57
右下の要素を計算 2行目 [3, 4] と 2列目 [8, 10] を使用
3×8 + 4×10 = 24 + 40 = 64
結果
[ 1 2 ] × [ 7 8 ] = [ 25 28 ]
[ 3 4 ] [ 9 10] [ 57 64 ]
覚えやすいコツ
- 「求めたい要素の行 × 求めたい要素の列 = 要素の値」
- 左の行列の横の列と、右の行列の縦の列を掛けて足す
- 指で線を引きながら計算すると間違えにくい
掛け算ができる条件
(m×n行列) × (p×q行列) ができるのは n = p のとき
結果は (m×q行列) になる
例:
- (2×3) × (3×2) = (2×2) ← できる
- (2×3) × (2×3) = できない(3 ≠ 2)
加減算、スカラー倍、積といった基本計算が行列のすべての土台になります。
次は、より応用的な操作について学んでいきましょう。
行列の応用的な操作|転置・単位・逆行列
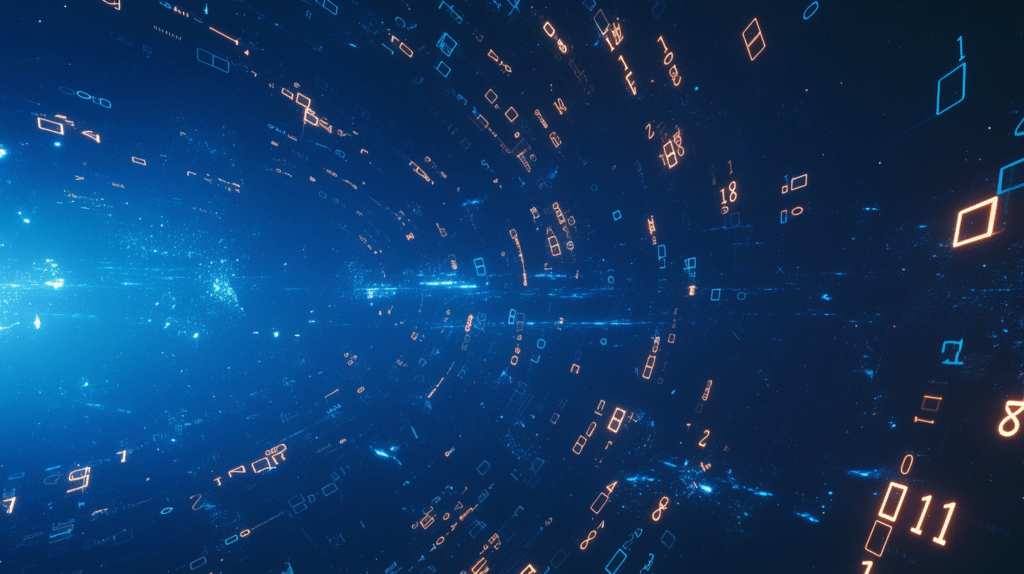
転置行列(てんちぎょうれつ)
転置行列とは、元の行列の「行と列を入れ替える」操作です。
基本的な転置
元の行列: 転置行列:
[ 1 2 3 ] → [ 1 4 ]
[ 4 5 6 ] [ 2 5 ]
[ 3 6 ]
転置のルール
- 1行目が1列目になる
- 2行目が2列目になる
- (i, j)の要素が(j, i)の位置に移動
記号 行列Aの転置行列は「A^T」または「A’」と書きます。
転置の具体例
例1:2×3行列
A = [ 1 2 3 ] A^T = [ 1 4 ]
[ 4 5 6 ] [ 2 5 ]
[ 3 6 ]
例2:正方行列
B = [ 1 2 ] B^T = [ 1 3 ]
[ 3 4 ] [ 2 4 ]
転置の性質
- (A^T)^T = A(転置の転置は元に戻る)
- (A + B)^T = A^T + B^T
- (AB)^T = B^T A^T(順序が逆になる)
実用例
- データの行と列を入れ替える
- ベクトルの内積計算
- 統計学での共分散行列計算
単位行列(たんいぎょうれつ)
単位行列は、掛け算で「元の行列を変えない」特別な行列です。数の世界の「1」のような役割を果たします。
2×2の単位行列
I = [ 1 0 ]
[ 0 1 ]
3×3の単位行列
I = [ 1 0 0 ]
[ 0 1 0 ]
[ 0 0 1 ]
単位行列の特徴
- 対角線(左上から右下への線)がすべて1
- それ以外の要素はすべて0
- どんな行列に掛けても元の行列のまま
計算例
[ 1 0 ] × [ a b ] = [ a b ]
[ 0 1 ] [ c d ] [ c d ]
[ a b ] × [ 1 0 ] = [ a b ]
[ c d ] [ 0 1 ] [ c d ]
記号と読み方
- 記号:I(Identity matrixの頭文字)
- 読み方:「アイ」または「単位行列」
逆行列(ぎゃくぎょうれつ)
逆行列は、元の行列と掛け合わせると単位行列になる特別な行列です。数の世界の「逆数」に相当します。
逆行列の定義
行列Aに対して、A × A^(-1) = I となる行列A^(-1)を「Aの逆行列」と言います。
2×2行列の逆行列の公式
元の行列:
A = [ a b ]
[ c d ]
逆行列:
A^(-1) = (1 / (ad - bc)) × [ d -b ]
[ -c a ]
重要な条件
- ad – bc ≠ 0 のときのみ逆行列が存在
- ad – bc を「行列式(determinant)」と呼ぶ
- 行列式が0の場合、逆行列は存在しない
具体的な計算例
例1:逆行列を求める
A = [ 2 1 ]
[ 3 2 ]
ステップ1:行列式を計算
ad - bc = 2×2 - 1×3 = 4 - 3 = 1
ステップ2:公式に当てはめる
A^(-1) = (1/1) × [ 2 -1 ] = [ 2 -1 ]
[-3 2 ] [-3 2 ]
ステップ3:検算
A × A^(-1) = [ 2 1 ] × [ 2 -1 ] = [ 1 0 ] = I ✓
[ 3 2 ] [-3 2 ] [ 0 1 ]
例2:逆行列が存在しない場合
B = [ 2 4 ]
[ 1 2 ]
行列式:2×2 – 4×1 = 4 – 4 = 0 → 逆行列は存在しない
逆行列の性質
- (A^(-1))^(-1) = A
- (AB)^(-1) = B^(-1) A^(-1)(順序が逆になる)
- (A^T)^(-1) = (A^(-1))^T
転置・単位行列・逆行列の理解は、線形代数の応用問題を解くために必須の知識です。
次は、これらの行列がどのように実際の問題で活用されているかを見ていきましょう。
行列の実際の活用例|身の回りでの応用
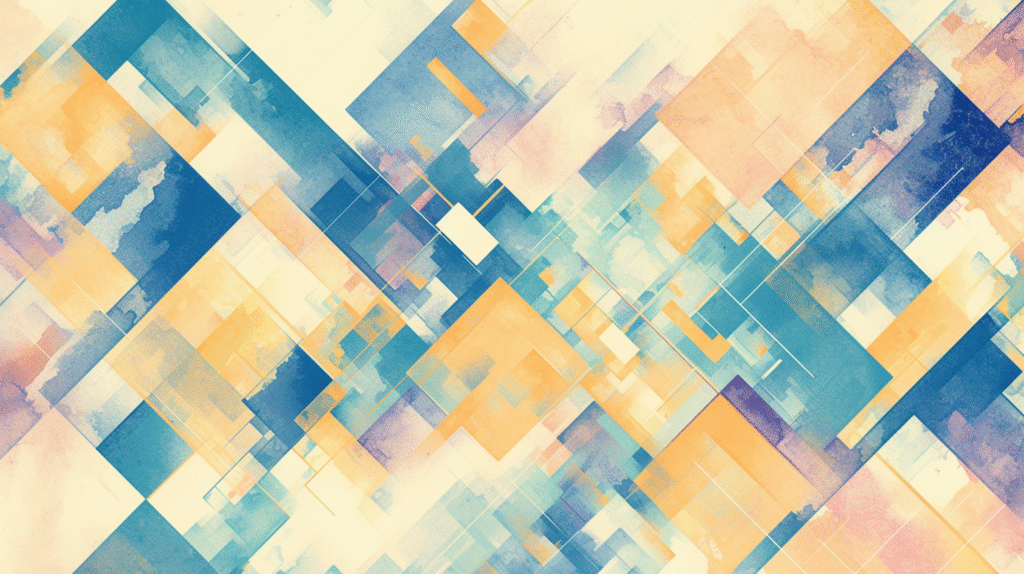
連立方程式の解法
行列を使うと、連立方程式をスマートに解くことができます。
従来の解法
2x + y = 7
3x + 2y = 12
この連立方程式を手計算で解くのは時間がかかりますね。
行列を使った解法
ステップ1:行列の形に変換
[ 2 1 ] [ x ] = [ 7 ]
[ 3 2 ] [ y ] [ 12 ]
これは AX = B の形(A:係数行列、X:未知数ベクトル、B:定数ベクトル)
ステップ2:逆行列を使って解く
X = A^(-1) B
ステップ3:逆行列を計算
A = [ 2 1 ] → A^(-1) = [ 2 -1 ]
[ 3 2 ] [-3 2 ]
ステップ4:解を求める
[ x ] = [ 2 -1 ] [ 7 ] = [ 2×7 - 1×12 ] = [ 2 ]
[ y ] [-3 2 ] [ 12 ] [-3×7 + 2×12] [ 3 ]
答え:x = 2, y = 3
メリット
- 計算が体系化されている
- コンピューターで自動計算しやすい
- 変数が多くても同じ方法で解ける
3Dグラフィックスでの変換
スマートフォンの画面回転やゲームの3D表示には、行列による座標変換が使われています。
回転変換の例
元の点の座標
点P (3, 4) を原点中心に45度回転させる
回転行列
R = [ cos45° -sin45° ] = [ 0.707 -0.707 ]
[ sin45° cos45° ] [ 0.707 0.707 ]
計算
[ x' ] = [ 0.707 -0.707 ] [ 3 ] = [ 0.707×3 - 0.707×4 ] = [ -0.707 ]
[ y' ] [ 0.707 0.707 ] [ 4 ] [ 0.707×3 + 0.707×4 ] [ 4.95 ]
結果 点P (3, 4) は回転後 (-0.707, 4.95) に移動
その他の変換
拡大・縮小
[ 2 0 ] → x方向に2倍、y方向に1倍
[ 0 1 ]
鏡像(左右反転)
[-1 0 ] → x座標の符号を逆にする
[ 0 1 ]
機械学習・AI分野での活用
現代のAI技術の多くは、行列計算に基づいています。
ニューラルネットワーク
- 重みパラメータを行列で表現
- 層間の計算が行列の積として実行
- 学習時の更新も行列演算
データ処理
学習データ(100人分の身長・体重・年齢)
[ 170 65 25 ]
[ 165 58 30 ]
[ 180 75 22 ]
...
[ 175 70 28 ]
各列が特徴量、各行がサンプルを表す行列
経済学・統計学での応用
産業連関表
農業 工業 サービス業
農業 [ 0.2 0.3 0.1 ]
工業 [ 0.3 0.4 0.2 ]
サービス[ 0.1 0.2 0.3 ]
各産業がどの産業からどれだけ投入を受けているかを表す
共分散行列
複数の変数間の関係を表す行列
株価の相関分析、リスク管理に使用
画像処理での活用
デジタル画像
- 画像は画素値の行列として表現
- フィルタ処理は行列の畳み込み演算
- 回転、拡大縮小は変換行列を適用
例:3×3の小さな画像
[ 100 150 200 ]
[ 120 180 220 ]
[ 140 160 180 ]
各数値が画素の明るさを表す
暗号技術での応用
公開鍵暗号
- RSA暗号では大きな行列の演算が基礎
- 量子コンピューター時代の新しい暗号も行列ベース
ブロックチェーン
- ハッシュ関数の計算に行列演算を活用
- 暗号通貨の安全性を支える技術
行列は単なる理論ではなく、私たちの日常生活を支える実用的な技術の基盤となっています。ス
マートフォンから人工知能まで、現代社会の多くの分野で活用されていることがわかります。
よくある質問と躓きやすいポイント
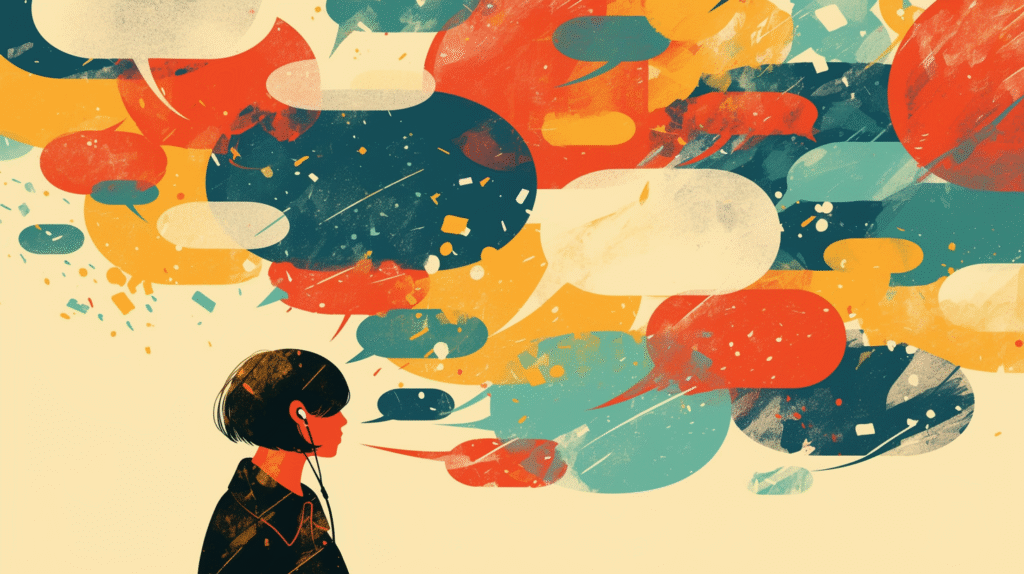
Q1: 行列の掛け算はなぜ順序が重要なの?
答え:A × B と B × A は一般的に異なる結果になるからです
具体例
A = [ 1 2 ] B = [ 5 6 ]
[ 3 4 ] [ 7 8 ]
A × B = [ 19 22 ]
[ 43 50 ]
B × A = [ 23 34 ]
[ 31 46 ]
理由
- 行列の積は「行と列の内積」で計算される
- A×BとB×Aでは、掛け合わせる要素の組み合わせが変わる
- 実用面では「変換の順序」を表すため、順序が重要
Q2: 逆行列が存在しない場合はどうする?
答え:疑似逆行列や他の解法を使います
逆行列が存在しない例
A = [ 2 4 ] (行列式 = 0)
[ 1 2 ]
対処法
- 疑似逆行列:完全な逆行列ではないが、近似解を求められる
- ガウス消去法:逆行列を使わない別の解法
- 特異値分解:より高度な数学的手法
Q3: 計算ミスを防ぐコツは?
行列計算のチェックポイント
サイズの確認
- 足し算・引き算:同じサイズかチェック
- 掛け算:左の列数 = 右の行数かチェック
計算順序
- 掛け算は必ず「行×列」の順序で
- 指や鉛筆で線を引きながら計算
検算方法
- 逆行列:A × A^(-1) = I になるかチェック
- 転置:(A^T)^T = A になるかチェック
まとめ
行列は決して難しい数学の理論だけのものではありません。
私たちの身の回りのテクノロジーを支える、とても実用的な道具です。
この記事で学んだ重要なポイント
- 行列は数を整理整頓する便利な仕組み
- 基本計算(加減算、スカラー倍、積)は規則的でわかりやすい
- 転置、単位行列、逆行列などの操作が応用の基礎
- スマートフォンからAIまで、現代技術の基盤
行列の理解は、数学だけでなく、現代のデジタル社会を理解するためにも重要なスキルです。
最初は計算が大変に感じるかもしれませんが、慣れてしまえば強力な問題解決ツールになります。
ぜひ基礎からしっかりと学んで、実際の問題に活かしてみてください。