NumPyのreshape()メソッドは、配列(ndarray)の「形(行数・列数など)」を変更するための関数です。
データ分析・機械学習・画像処理など、あらゆる場面で「データの並び方を変えたい」ことはよくあります。そのときに活躍するのがこのreshape()です。
arr.reshape(行数, 列数)
この記事では、reshape()の基本構文、よくあるエラー、次元の自動計算、実務で使える応用テクニックまで説明します。
reshapeの基本構文と使い方
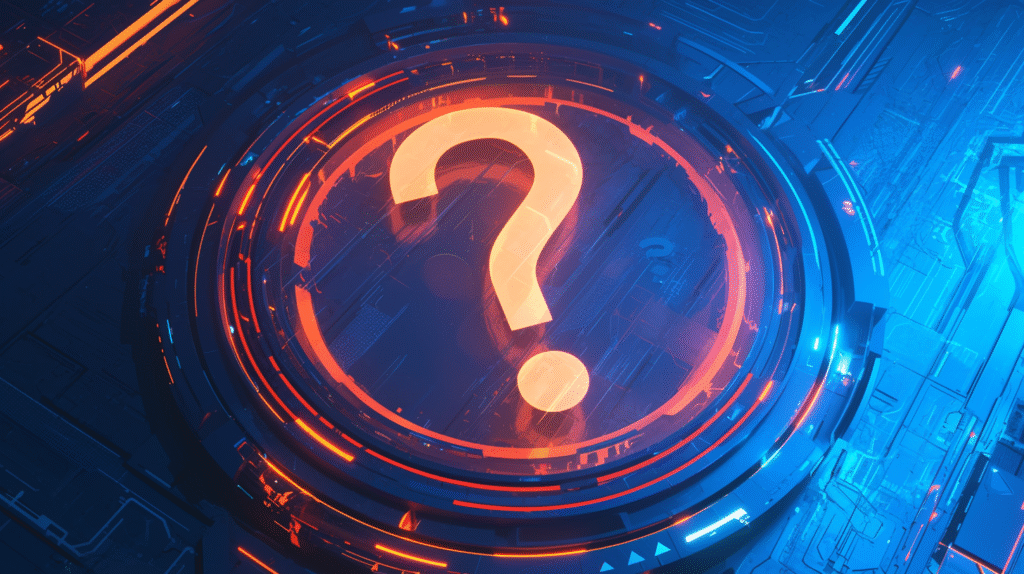
基本の考え方
重要なポイント:
- 元の配列の要素数は変えずに、形だけ変える
- 中身のデータは同じで、並び方だけが変わる
基本構文
new_arr = arr.reshape(新しい形状)
例1:1次元から2次元への変換(6個 → 2行3列)
import numpy as np
# 1次元配列を作成
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
print(f"元の配列: {arr}")
print(f"元の形状: {arr.shape}") # 結果: (6,)
# 2行3列に変換
reshaped = arr.reshape(2, 3)
print("変換後の配列:")
print(reshaped)
# 結果:
# [[1 2 3]
# [4 5 6]]
print(f"変換後の形状: {reshaped.shape}") # 結果: (2, 3)
どうやって変換される?
元: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
↓
変換後:
[[1, 2, 3],
[4, 5, 6]]
左から順番に、指定した形に当てはめられます。
例2:1次元から3次元への変換
# 12個の要素を持つ配列
arr = np.arange(12) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
print(f"元の配列: {arr}")
# 2×3×2の3次元配列に変換
reshaped_3d = arr.reshape(2, 3, 2)
print("3次元に変換:")
print(reshaped_3d)
# 結果:
# [[[ 0 1]
# [ 2 3]
# [ 4 5]]
# [[ 6 7]
# [ 8 9]
# [10 11]]]
例3:2次元から1次元への変換(平坦化)
# 2次元配列を作成
matrix = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print("元の2次元配列:")
print(matrix)
# 1次元に変換
flattened = matrix.reshape(6) # または matrix.reshape(-1)
print(f"1次元に変換: {flattened}")
# 結果: [1 2 3 4 5 6]
まとめ
reshape()は「要素数を保ったまま形状だけ変える」関数- 中身のデータの順番は保たれる
reshapeで自動的に次元数を計算(-1の使い方)

-1を使った自動計算
1つの次元を-1にすると、他の次元から自動的に計算されます!
import numpy as np
# 12個の要素を持つ配列
arr = np.arange(12)
print(f"元の配列: {arr}")
# 3行、列数は自動計算
result1 = arr.reshape(3, -1)
print(f"3行、列数自動: {result1.shape}") # 結果: (3, 4)
print(result1)
# 結果:
# [[ 0 1 2 3]
# [ 4 5 6 7]
# [ 8 9 10 11]]
# 4行、列数は自動計算
result2 = arr.reshape(4, -1)
print(f"4行、列数自動: {result2.shape}") # 結果: (4, 3)
print(result2)
# 結果:
# [[ 0 1 2]
# [ 3 4 5]
# [ 6 7 8]
# [ 9 10 11]]
計算の仕組み:
- 全要素数:12個
- 3行指定 → 列数 = 12 ÷ 3 = 4列
- 4行指定 → 列数 = 12 ÷ 4 = 3列
注意:複数の-1は使えない
# これはエラーになる
try:
arr.reshape(-1, -1) # ❌ ValueError
except ValueError as e:
print(f"エラー: {e}")
理由: どちらも「おまかせ」だと、計算できないため
よく使うパターン
パターン1:flatten(1次元化)
matrix = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
flattened = matrix.reshape(-1)
print(f"1次元化: {flattened}") # 結果: [1 2 3 4 5 6]
パターン2:列ベクトル化(縦一列に並べる)
arr = np.array([1, 2, 3, 4])
column_vector = arr.reshape(-1, 1)
print("列ベクトル:")
print(column_vector)
# 結果:
# [[1]
# [2]
# [3]
# [4]]
print(f"形状: {column_vector.shape}") # 結果: (4, 1)
パターン3:行ベクトル化(横一列に並べる)
arr = np.array([1, 2, 3, 4])
row_vector = arr.reshape(1, -1)
print("行ベクトル:")
print(row_vector) # 結果: [[1 2 3 4]]
print(f"形状: {row_vector.shape}") # 結果: (1, 4)
まとめ
-1はreshapeの「おまかせ指定」- 柔軟な形状変換にとても便利
よくあるエラーと対策
エラー1:reshapeできない数を指定
import numpy as np
# 10個の要素を持つ配列
arr = np.arange(10)
print(f"配列: {arr}")
print(f"要素数: {arr.size}") # 結果: 10
try:
# 3×4=12なので、10個の要素では作れない
reshaped = arr.reshape(3, 4)
except ValueError as e:
print(f"エラー: {e}")
print("10個の要素を3×4(12個)には変形できません")
# 正しい例
correct_reshape = arr.reshape(2, 5) # 2×5=10なのでOK
print("正しい変形:")
print(correct_reshape)
対策: 要素数を確認してから、掛け算が合う形状を指定する
def suggest_shapes(arr):
"""可能な形状を提案する関数"""
size = arr.size
print(f"要素数: {size}")
print("可能な形状:")
for i in range(1, size + 1):
if size % i == 0:
print(f" {i}行 × {size // i}列")
# 使用例
arr = np.arange(12)
suggest_shapes(arr)
# 結果:
# 要素数: 12
# 可能な形状:
# 1行 × 12列
# 2行 × 6列
# 3行 × 4列
# 4行 × 3列
# 6行 × 2列
# 12行 × 1列
エラー2:reshape後の配列に代入し忘れ
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
print(f"元の形状: {arr.shape}") # 結果: (6,)
# 間違い:代入していない
arr.reshape(2, 3)
print(f"reshapeした後の形状: {arr.shape}") # 結果: (6,) ← 変わっていない!
# 正しい方法1:代入する
arr_reshaped = arr.reshape(2, 3)
print(f"正しく代入した形状: {arr_reshaped.shape}") # 結果: (2, 3)
# 正しい方法2:元の変数に代入
arr = arr.reshape(2, 3)
print(f"元の変数に代入した形状: {arr.shape}") # 結果: (2, 3)
重要なポイント: reshape()は非破壊的な関数です。元の配列は変更せず、新しい配列を返します。
エラー3:転置と混同する
import numpy as np
# 2×3の配列
matrix = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print("元の配列:")
print(matrix)
print(f"形状: {matrix.shape}") # 結果: (2, 3)
# 間違い:行と列を入れ替えたいのにreshapeを使う
wrong = matrix.reshape(3, 2)
print("reshapeで3×2に変更:")
print(wrong)
# 結果:
# [[1 2]
# [3 4]
# [5 6]]
# 正しい:転置を使う
correct = matrix.T # または matrix.transpose()
print("転置(正しい行列の入れ替え):")
print(correct)
# 結果:
# [[1 4]
# [2 5]
# [3 6]]
print(f"転置後の形状: {correct.shape}") # 結果: (3, 2)
使い分け:
- reshape:要素の順番を保ったまま形状変更
- 転置(transpose):行と列を入れ替える
まとめ
- エラーの原因はほとんどが「要素数が合わない or 代入忘れ」
- 転置が必要な場合は
.Tを使う
実務でよくあるreshape活用例

活用例1:画像処理(28×28の画像を1次元ベクトルに)
import numpy as np
# 28×28の画像データ(手書き数字など)
image = np.random.randint(0, 256, size=(28, 28))
print(f"元の画像形状: {image.shape}") # 結果: (28, 28)
print(f"画素数: {image.size}") # 結果: 784
# 機械学習用に1次元ベクトルに変換
flattened_image = image.reshape(-1)
print(f"1次元化後の形状: {flattened_image.shape}") # 結果: (784,)
# 複数の画像をまとめて処理
num_images = 100
images = np.random.randint(0, 256, size=(num_images, 28, 28))
print(f"複数画像の形状: {images.shape}") # 結果: (100, 28, 28)
# 各画像を1次元化(100枚 × 784ピクセル)
flattened_images = images.reshape(num_images, -1)
print(f"一括1次元化後: {flattened_images.shape}") # 結果: (100, 784)
活用例2:機械学習の特徴量整形
import numpy as np
# 時系列データの例(10日間 × 24時間 × 3つの測定値)
time_series = np.random.randn(10, 24, 3)
print(f"時系列データの形状: {time_series.shape}") # 結果: (10, 24, 3)
# 機械学習用に2次元に変換(サンプル数 × 特徴数)
# 各日を1つのサンプルとして、24×3=72の特徴量に
X = time_series.reshape(10, -1)
print(f"特徴量行列の形状: {X.shape}") # 結果: (10, 72)
# または、各時刻を1つのサンプルとして扱う場合
# 10×24=240のサンプル、各サンプルは3つの特徴量
X_hourly = time_series.reshape(-1, 3)
print(f"時刻ごとの特徴量: {X_hourly.shape}") # 結果: (240, 3)
活用例3:CSVやExcelの行列整形
import numpy as np
# 長い1次元データを読み取った場合
csv_data = np.arange(1, 21) # 1から20までのデータ
print(f"元のデータ: {csv_data}")
# 4行5列の表に整形
table = csv_data.reshape(4, 5)
print("表形式に整形:")
print(table)
# 結果:
# [[ 1 2 3 4 5]
# [ 6 7 8 9 10]
# [11 12 13 14 15]
# [16 17 18 19 20]]
# カラム名をつけて表示(pandas風)
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(table, columns=[f'列{i+1}' for i in range(5)])
print("DataFrame形式:")
print(df)
活用例4:3Dデータの可視化準備
import numpy as np
# 3次元データ(例:医療画像、気象データなど)
volume_data = np.random.randn(10, 10, 10)
print(f"3次元データ: {volume_data.shape}")
# 2次元スライスとして表示するために変形
# 各スライス(10×10)を横に並べて表示
slices_horizontal = volume_data.reshape(10, -1)
print(f"横並びスライス: {slices_horizontal.shape}") # 結果: (10, 100)
# 各スライスを縦に並べて表示
slices_vertical = volume_data.transpose(2, 0, 1).reshape(-1, 10)
print(f"縦並びスライス: {slices_vertical.shape}") # 結果: (100, 10)
活用例5:バッチ処理でのデータ整形
import numpy as np
# ニューラルネットワーク用のデータ準備
# バッチサイズ32、シーケンス長20、特徴量10
batch_data = np.random.randn(32, 20, 10)
print(f"バッチデータ: {batch_data.shape}")
# RNN用に2次元に変換(全時刻をまとめて処理)
rnn_input = batch_data.reshape(-1, 10)
print(f"RNN入力形状: {rnn_input.shape}") # 結果: (640, 10)
# 処理後に元の形状に戻す
output = rnn_input # 何らかの処理
output_reshaped = output.reshape(32, 20, 10)
print(f"処理後の形状: {output_reshaped.shape}") # 結果: (32, 20, 10)
応用テクニック
複雑な形状変換
import numpy as np
# 6×8の画像を2×2のブロックに分割
image = np.arange(48).reshape(6, 8)
print("元の画像:")
print(image)
# 2×2ブロックに分割(3×4個のブロック)
blocks = image.reshape(3, 2, 4, 2).transpose(0, 2, 1, 3).reshape(12, 2, 2)
print(f"ブロック数: {blocks.shape[0]}")
print("最初のブロック:")
print(blocks[0])
条件付きreshape
import numpy as np
def smart_reshape(arr, target_rows):
"""要素数に応じて柔軟にreshapeする関数"""
total_elements = arr.size
if total_elements % target_rows != 0:
# パディングを追加して調整
padding_needed = target_rows - (total_elements % target_rows)
arr_padded = np.pad(arr, (0, padding_needed), constant_values=0)
total_elements = arr_padded.size
else:
arr_padded = arr
cols = total_elements // target_rows
return arr_padded.reshape(target_rows, cols)
# 使用例
data = np.arange(23) # 23個の要素(素数)
result = smart_reshape(data, 5)
print("柔軟なreshape結果:")
print(result)
まとめ
| 操作内容 | コマンド例 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 1次元 → 2次元 | arr.reshape(2, 3) | 表形式に整理 |
| 自動で次元を決める | arr.reshape(3, -1) | 一方向のサイズが決まっている |
| 1次元化(flatten) | arr.reshape(-1) | 機械学習の前処理 |
| 列ベクトル化 | arr.reshape(-1, 1) | 数学的な計算 |
| 行ベクトル化 | arr.reshape(1, -1) | 横一列に表示 |
| 転置(行列の入れ替え) | arr.T | 行と列を入れ替え |
トラブルシューティング早見表
| エラー内容 | 原因 | 解決方法 |
|---|---|---|
ValueError: cannot reshape | 要素数が合わない | arr.sizeを確認し、掛け算が合う形状を指定 |
| 形状が変わらない | 代入し忘れ | arr = arr.reshape(...) で代入 |
| 期待した結果にならない | 転置と混同 | 行列の入れ替えならarr.Tを使用 |







